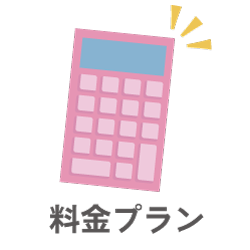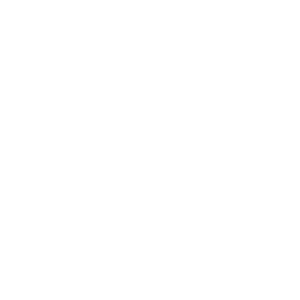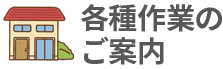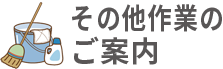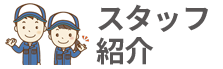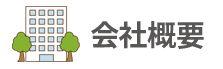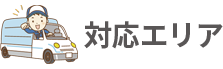【身寄りのない人はどうなる?】「行旅死亡人制度」とは?葬儀・火葬の流れを解説
2025年09月15日身寄りのない人が亡くなった場合、
「お葬式は誰がするの?」「遺骨はどうなるの?」
と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。
実は、日本には「行旅死亡人制度」という仕組みがあり、
遺体を放置することなく、最低限の葬送が行われるよう法律で定められています。
今回は、この制度の内容や流れ、生前に準備できることについて分かりやすく解説します。
行旅死亡人制度とは?
「行旅死亡人制度(こうりょしぼうにんせいど)」とは、身寄りがない方や、
親族に引き取りを拒否された方が亡くなった際に、
市区町村が責任をもって火葬や埋葬を行う仕組みです。
根拠となるのは「行旅病人及行旅死亡人取扱法」という明治時代に制定された法律で、
今もなお運用されています。
この制度の目的は、遺体を社会的に放置せず、
最低限の尊厳をもって弔うことにあります。
たとえ親族がいない場合でも、
火葬や納骨は必ず行われるため、遺体が放置されることはありません。
ただし、通夜や告別式といった葬儀は含まれておらず、
最低限の火葬と埋葬にとどまるのが特徴です。
近年は高齢化や単身世帯の増加により、この制度の利用は増えています。
ニュースなどで「無縁仏」という言葉を耳にすることもありますが、
その背景には行旅死亡人制度が関わっているケースも少なくありません。
実際の流れ
行旅死亡人制度が適用される場合、流れは次のようになります。
まず、病院や施設、自宅、路上などで死亡が確認されると、
警察や医療機関が身元確認を行い、親族がいるかどうか調査します。
親族に連絡が取れない、あるいは引き取りを拒否された場合、
その方は「行旅死亡人」として扱われます。
次に、市区町村へと手続きが引き継がれます。
本来は親族が提出する死亡届も、市区町村長が代理で行う形になります。
その後、自治体が火葬を手配し、
遺骨は市が管理する合同墓や無縁墓に埋葬されるのが一般的です。
さらに、財布や身分証など所持品から身元が分かる可能性がある場合は、
官報や自治体の掲示板に公告されます。
一定期間内に親族や関係者が名乗り出れば、遺骨や遺品が引き渡されます。
逆に、期限内に誰も現れなければ、そのまま自治体が管理を続けることになります。
費用は誰が負担するのか?
行旅死亡人制度における火葬や納骨の費用は、原則として市区町村が一時的に立て替えます。
遺体搬送費や火葬費、納骨費用などが含まれ、最低限の葬送費用は自治体が負担する仕組みです。
ただし、後から相続人や扶養義務者が見つかった場合、
自治体はその人に費用を請求することができます。
つまり、完全に「誰にも費用がかからない」というわけではなく、
遠縁の親族が請求対象となる可能性もあるのです。
また、この制度で行われるのはあくまで火葬と納骨に限定されており、
通夜や告別式などの一般的な葬儀は含まれていません。
お経をあげてもらう、お墓を建ててもらうといった希望は反映されず、
「最低限の葬送に限られる」という点を理解しておく必要があります。
制度の限界と注意点
行旅死亡人制度は、人としての尊厳を最低限守るために存在していますが、
限界もあります。
まず、通夜や告別式といった儀式は行われず、
葬儀そのものが簡略化される点です。
したがって「自分の葬儀をしてほしい」と願っていても、
この制度だけでは実現できません。
遺品についても、価値があるものや身元確認に必要なもの以外は、
基本的に処分されます。
大切にしていた品々が丁寧に整理されるとは限らず、
本人の希望は尊重されにくいのが現実です。
また、遺骨は合同墓や無縁墓に納められるため、
個別に供養してもらうことは難しくなります。
後から友人や親族が訪れたいと思っても、
場所が分からなかったり、参拝が制限されている場合もあります。
こうした点からも、「最低限の制度に過ぎない」ということを理解しておく必要があります。
生前に準備できること
身寄りがない方や、将来ひとりになるかもしれないと感じる方にとっては、
生前の準備がとても重要です。
例えば「死後事務委任契約」を結んでおけば、
信頼できる人や専門業者に葬儀や納骨、遺品整理まで依頼できます。
また、葬儀社との事前契約(互助会など)を利用すれば、
希望する形の葬儀をあげてもらうことも可能です。
さらに、遺言やエンディングノートに希望を書き残しておくことも大切です。
「自分の遺骨はどうしてほしいか」「どのような葬儀を望むか」
を明確にしておくことで、後に関わる人たちが迷わず行動できます。
行旅死亡人制度は社会的に必要不可欠な仕組みですが、
あくまで「最低限」にとどまります。
自分らしい最期を迎えるためには、
生前整理や契約といった準備をしておくことが安心につながります。
✅ まとめ
行旅死亡人制度は、身寄りのない人が亡くなった場合でも火葬・納骨を必ず行う仕組みであり、
最低限の尊厳を守る大切な制度です。
しかし、内容は簡素で、葬儀や供養の希望は反映されにくいという限界があります。
だからこそ、生前に「死後事務委任契約」や「エンディングノート」などで備えておくことが、
自分らしい最期につながります。もしもの時に備えて、早めに準備を始めてみてはいかがでしょうか。
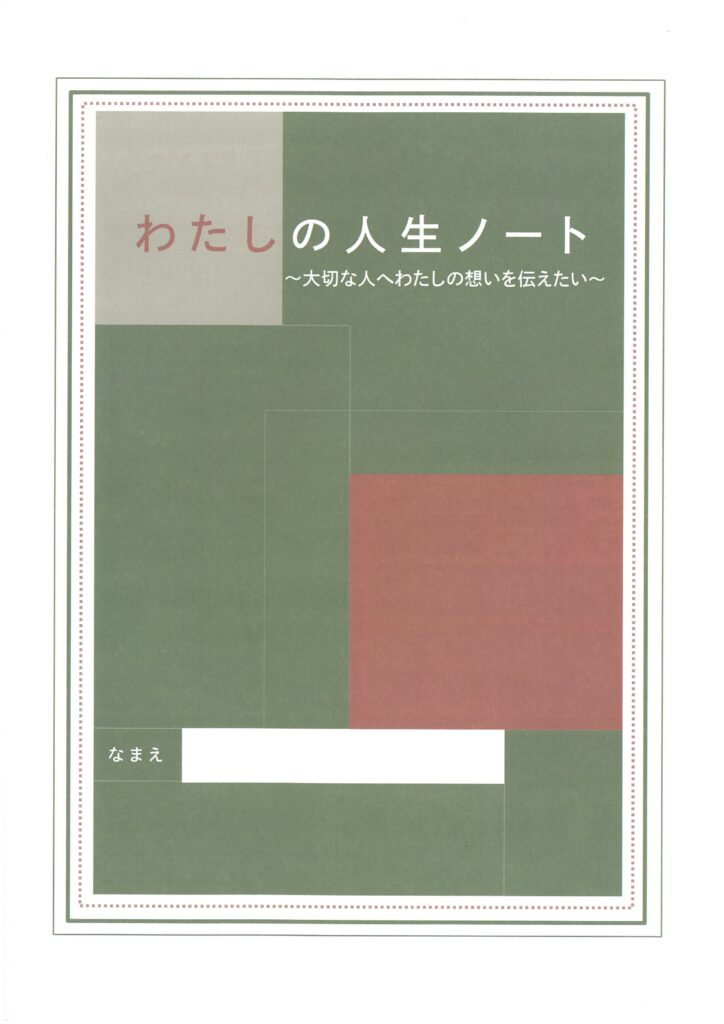
遺品整理士 倉島 新吾
東海3県~愛知県・岐阜県・三重県~ 九州エリア~鹿児島県・宮崎県・熊本県~
スケジュールに空きがあれば即日の対応も可能。お見積り無料です。
遺品整理、生前整理、空き家整理、ゴミ屋敷、汚部屋、特殊清掃(事故現場・孤独死現場)、
ウイルスの除菌消臭(新型コロナ対応)、ペット臭(猫屋敷など)、不用品買取値引き、解体前や退去前の残置整理 etc…
自転車・バイク・仏壇・神棚・マットレス・シンク・物干し台・物置の解体、撤去・エアコンの取外し・庭木の伐採・草刈りなどなんでもご相談ください!
TEL:0120-379-540 担当者直通:070-1327-8548
メール・LINEからは、24時間365日ご相談を受け付けしております。
Twitterも日々更新中♪
新着記事
- [作業実績] [2026.01.28] 日進市:空家整理/戸建/2LDK
- [コラム] [2026.01.21] 「猫屋敷」の孤独に終止符を!プロの【まごころ特殊清掃】で愛猫と「普通の暮らし」を取り戻しませんか?【カメシタのハウスクリーニング】
- [作業実績] [2026.01.21] 東浦町:ゴミ屋敷清掃/賃貸
- [コラム] [2026.01.14] 名古屋市中村区:ゴミ屋敷整理/空家整理/戸建
- [コラム] [2026.01.14] 【多頭飼育ペットの遺品整理】母の愛は手放さない。途方に暮れるあなたへ、命と心を癒すプロの「まごころ」解決法