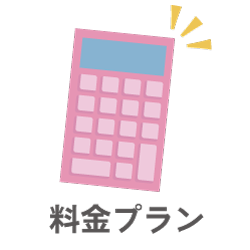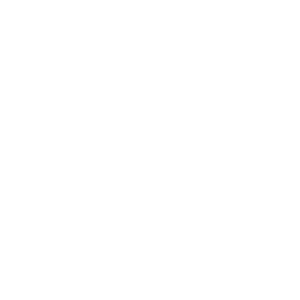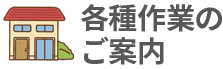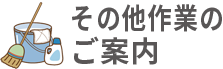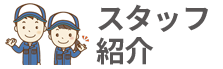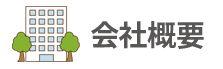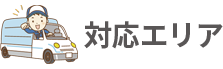【急増中】2024年 相続登記の義務化で変わる意識と行動|いま知っておくべき手続きと対策とは?
2025年05月05日目次
2024年から何が変わった?相続登記義務化のポイント
2024年4月1日から施行された新制度により、
不動産を相続した際の登記手続きが義務となりました。
これまでは任意だったため、「そのうちでいい」と放置されることも多く、
名義が故人のまま何年も経過するケースが少なくありませんでした。
しかし今後は、相続によって不動産を取得した人は取得を知った日から3年以内に相続登記を行わなければなりません。
怠ると10万円以下の過料(罰金)が科される可能性があります。
この義務化は単に罰則を与えるためではなく、
「次の世代に不安を残さないための第一歩」です。
特に空き家や放置された土地を相続したご家族にとっては、
登記を通じて財産の管理や処分がスムーズになり、
結果として家族間のトラブルを防ぐことにもつながります。
相続が発生したら、まずは登記のことを意識する。
そんな新しい常識が、今始まっています。
義務化の施行日はいつ?罰則の内容は?
相続登記の義務化は、2024年4月1日に施行されました。
対象となるのはこの日以降の相続だけでなく、
過去の相続で登記が未了のものも含まれます。
たとえば、10年前に親を亡くして不動産を引き継いだものの、
名義変更をしていない
そんなケースも、2024年4月1日以降は
「知った日から3年以内」に手続きをする必要があります。
義務に違反すると、最大10万円の過料が科される可能性があります。
この罰則は行政からの指導というよりも、
法務局からの命令に従わなかった場合に科される正式な処分です。
「うっかり忘れていた」「知らなかった」という理由では免除されないため、
今一度、手元の不動産の登記状況を確認することが大切です。
未来のトラブルを避けるためにも、早めの行動を心がけましょう。
なぜ義務化された?背景にある社会問題
相続登記が義務化された背景には、
日本全体で深刻化している「所有者不明土地問題」があります。
これは、不動産の相続が発生しても登記がされず、
誰がその土地や建物の所有者か分からなくなる現象です。
国土交通省の調査によると、
所有者不明の土地は九州全体の面積を上回る規模にまで拡大しており、
公共事業の妨げや災害時の復旧遅れといった、社会的損失も発生しています。
なぜこのような事態になったのか。
それは「相続登記は義務ではない」という制度のスキマが原因でした。
登記をしなくてもすぐに困ることはないと考え、
何世代にもわたって放置されるケースが増えていったのです。
今回の法改正は、こうした課題に終止符を打つための大きな一歩です。
ひとりひとりの行動が、将来の安心と地域社会の健全な発展につながるのです。
“誰が”対象になるのか?知らないと損する対象者の条件
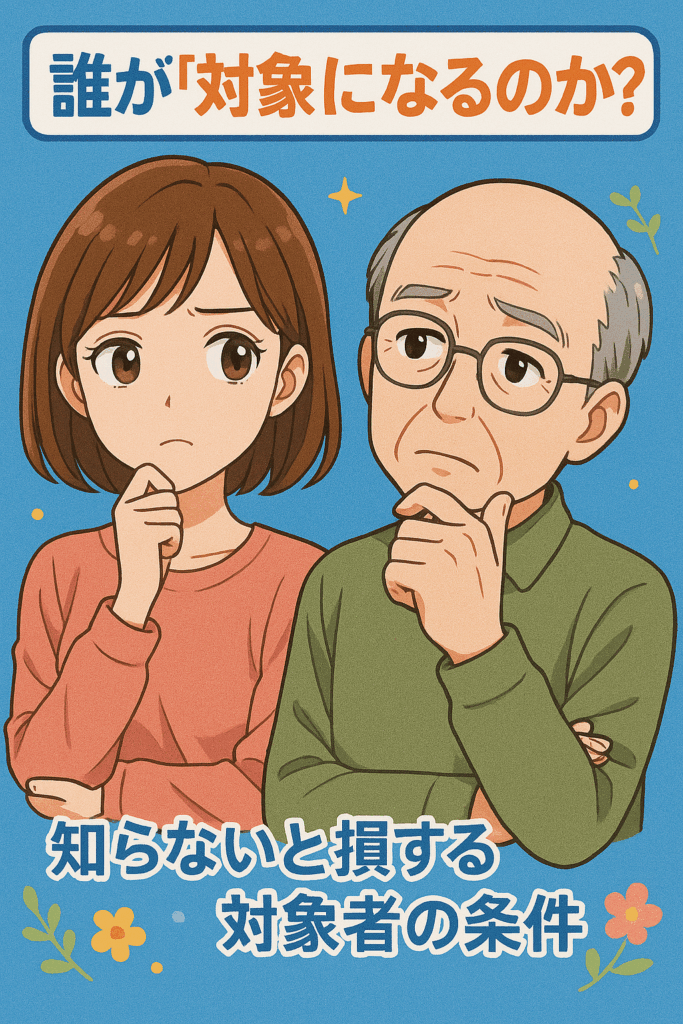
相続登記の義務は、「相続によって不動産を取得した人すべて」が対象です。
ここで注意が必要なのは、
「取得したつもりがなくても、義務が発生するケースがある」ということです。
たとえば、遺産分割協議で
「兄が不動産を引き継ぐことになった」と決まっていても、
正式な登記が済んでいなければ、他の兄弟にも義務が生じる可能性があります。
また、「相続放棄したから関係ない」と思っていても、
家庭裁判所での正式な放棄手続きをしていなければ、義務の対象になることも。
さらに、「長男が住んでいるから」「家族間の暗黙の了解があるから」
というような理由では法的に登記義務を免れることはできません。
義務の有無は、自分の判断ではなく法的な基準で決まるもの。
心配な場合は、早めに司法書士などの専門家に相談しましょう。
2024年以降、増えている“意識の変化”とは?
2024年の相続登記義務化をきっかけに、
これまで後回しにされがちだった「実家」や「空き家」の問題に、
真剣に向き合う人が増えています。
「うちはまだ大丈夫」「兄が住んでいるから…」と、
なんとなく曖昧なままでいた人も、法律の改正を通して
「今のうちに整理しておいたほうがいい」と実感し始めたのです。
とくに話題になっているのが、
“登記を終えてこそ相続は完了”という考え方の広がり。
不動産の名義をそのままにしておくと、
売却・管理・処分などすべての手続きに支障が出ます。
だからこそ、登記という“形ある手続き”をもって、
家族の未来を整えておこうとする人が増えているのです。
「相続=財産を受け取ること」ではなく、
「きちんと責任を整理して、次につなぐこと」へ。
その意識の変化が、今、大きく進んでいます。
「親の家をどうするか」を考える人が急増中
かつては「とりあえず残しておけばいい」とされていた親の家。
ですが、相続登記の義務化をきっかけに、
「このままでいいのか?」と考える人が急増しています。
名義が故人のままでは、売ることも貸すことも、リフォームもできません。
相続人の誰が管理するのか、
どう活用するのかその前提として必要なのが、相続登記なのです。
「兄弟と話し合うきっかけになった」「不動産会社に相談した」など、
登記を軸に家族の対話が始まったという声も多く聞かれます。
親の家を放置しておくと、将来の世代に重い負担となってしまう可能性も。
だからこそ、登記を“義務”ではなく“家族の問題に向き合うきっかけ”と捉え、
いま一歩を踏み出す人が増えているのです。
その選択は、きっと“未来の自分”にも感謝されるはずです。
“登記を終えて初めて相続が完了する”という認識
「相続は遺産分割が終われば完了」という認識は、
いま大きく変わりつつあります。
実際には、どれだけ話し合いが整っていても、
不動産の名義変更=相続登記を終えなければ、
法的にも実務的にも「相続は終わっていない」状態です。
名義が故人のままでは、不動産を売却することも貸すこともできませんし、
災害や事故があったときに責任の所在が不明瞭になることもあります。
また、将来的に次の相続が発生した際、
登記が未了だと「二重相続」のような複雑な問題に発展しかねません。
いまでは「登記が済んで初めて相続が完了する」という考え方が常識になりつつあります。
「面倒だから後回しに…」ではなく、
「今やることで安心が生まれる」
――そんな前向きな行動が広がっています。
不動産を「資産」ではなく「負動産」と感じる世代も
一昔前までは「家を持っている=資産を持っている」
という認識が一般的でしたが、今では状況が大きく変わってきています。
空き家や地方の不動産など、手間とコストばかりかかる物件に対し、
「これは本当に資産なのだろうか?」と疑問を抱く人が増えてきました。
実際、相続した土地や建物が使い道もなく放置され、
固定資産税や草刈り・修繕の管理費だけがかかってしまうケースも多く見られます。
こうした不動産は、
もはや“資産”ではなく“負動産”として扱われるようになってきているのです。
相続登記の義務化によって、
「自分は何を引き継ぐのか」「何を手放すのか」を見極める視点も育っています。
将来を見据えた“持たない選択”も、家族への愛の形かもしれません。
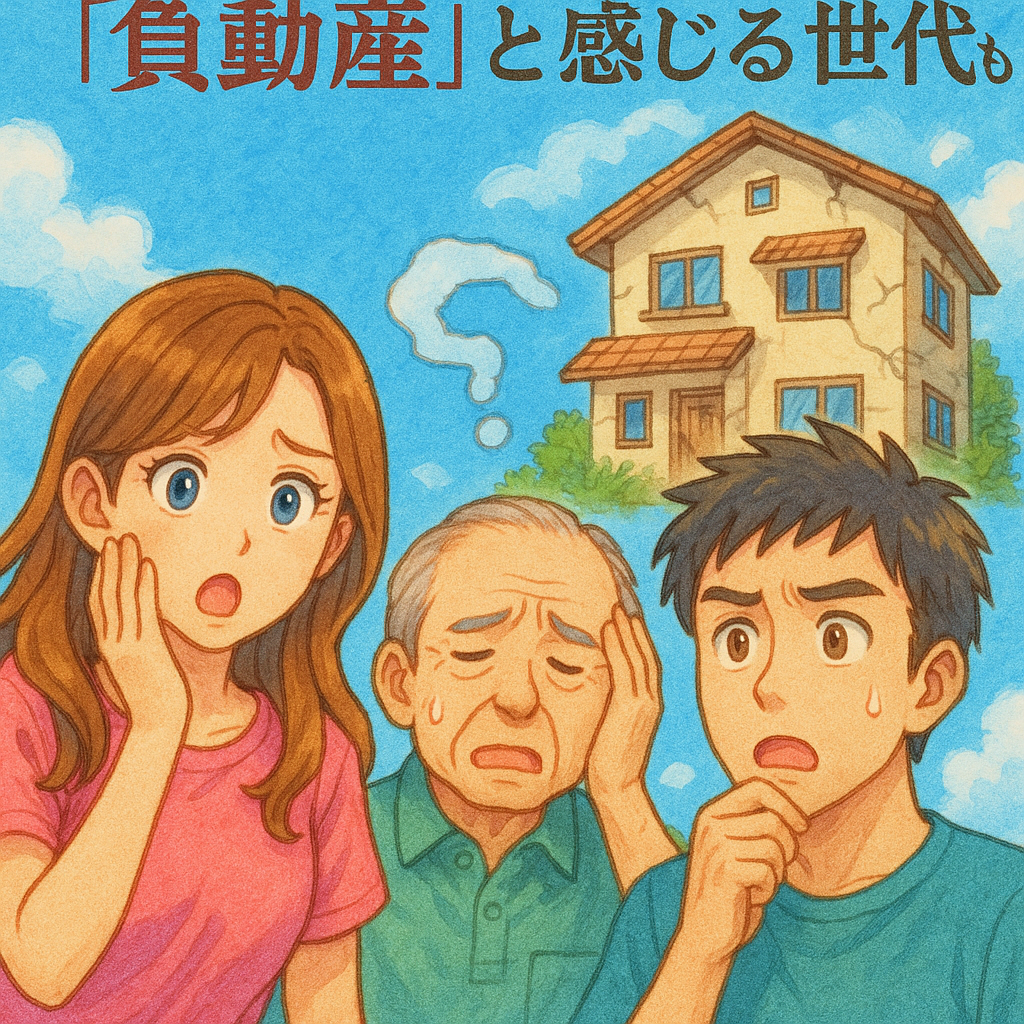
いますぐ確認したい!相続登記が必要かチェックする方法
「うちは相続登記なんて関係ない」と思っている方こそ、一度確認してみてください。
実は、名義変更をしていない不動産がある家庭は想像以上に多く、
知らぬ間に相続登記の義務対象になっているケースもあります。
確認の第一歩は、不動産の「登記簿謄本(全部事項証明書)」を取り寄せること。
法務局の窓口や郵送申請、
または登記情報提供サービス(ネット)から誰でも取得可能です。
その書類の「所有者欄」に故人の名前が記載されていれば、
相続登記が未了である証拠です。
また、登記がされていても共有名義になっていたり、
実態と異なる記載になっている場合もあります。
これらは後々トラブルの元になりがちです。
面倒な印象があるかもしれませんが、
「今確認する」ことが、家族の未来を守る小さな一歩になります。
不動産登記簿の見方と確認手順
不動産登記簿は「表題部」「甲区(所有権)」「乙区(抵当権など)」
の3つで構成されています。まず確認すべきは甲区の所有者欄。
ここに書かれている氏名が「亡くなった親の名前」であれば、登記が未了です。
また、「取得原因」欄に「相続」と記載があるかも大切なチェックポイントです。
登記簿の取得は、全国どこでも可能で、手続きも簡単です。
お近くの法務局に行くか、
オンラインの登記情報提供サービス(有料)で調べられます。
「専門的で難しそう」と感じる場合は、
司法書士などの専門家に代行を依頼することも可能です。
間違った情報のまま放置されていることもあるので、
できれば一度チェックしてみることをおすすめします。
自分の目で確かめることが安心につながります。
「登記が未了」かどうかはここでわかる
登記が未了かどうかを見極めるポイントは、
登記簿の所有者が誰か、そして取得原因が何かの2点です。
たとえば、「所有者」欄に亡くなった方の名前がそのまま載っており、
「取得原因」が「売買」「贈与」となっていて「相続」の記載がない場合、
それは相続登記がされていない状態です。
ここで注意したいのは、「すでに相続人が住んでいる」「税金を払っている」
といった事実があっても、それは登記の完了を意味しないということです。
第三者から見たとき、「この不動産の正式な所有者は誰か」が不明になってしまいます。
これが「所有者不明土地問題」の原因でもあります。
登記は「形式だけのもの」ではなく、
所有権を明確にし、安心して管理・活用するための大切なステップなのです。
名義変更と登記は別物!間違いやすいポイント解説
相続が発生した際、
「家は長男が継ぐって決まっているから大丈夫」という話はよく聞きます。
しかし、それがどれだけ家族内で合意されていても、
登記がされていなければ法的には何も変わっていないということになります。
特に誤解されやすいのが、
「市役所で名義変更をしたからもう完了した」というケース。
実は、役所の手続き(たとえば納税通知書の送付先変更)と、
法務局での相続登記はまったく別の手続きです。
役所では税金の請求先が変わるだけで、登記名義はそのままです。
こうした“認識のズレ”が、のちのち売却や貸出、
相続人間の争いに発展してしまうこともあります。
正式に登記することで、誰がどの不動産を所有しているのかを明確にし、
家族間の信頼関係を守ることにもつながるのです。
相続登記の手続き方法と頼れる専門家
相続登記は、自分で手続きすることもできますが、
書類の準備や手続きの正確さが求められるため、
専門家のサポートを受ける方も少なくありません。
とくに相続人が複数いるケースや、遺産分割協議が必要な場合には、
思わぬトラブルや書類の不備が生じやすくなります。
登記が受理されないと何度もやり直すことになり、
精神的な負担も大きくなりがちです。
そのため、「一度で正確に済ませたい」「忙しくて自分では手が回らない」
という方には、司法書士や行政書士などの専門家への依頼が安心です。
この章では、自分で手続きをする場合の基本的な流れに加え、
専門家に依頼する際の選び方や、
費用の目安についても具体的にご紹介していきます。
相続という大切な手続きを、少しでもスムーズに、
そして安心して進めるためにお役立てください。
自分でやる場合:必要書類と手続きの流れ
相続登記を自分で行う際は、まず必要な書類をしっかり揃えることが重要です。
代表的な書類は、
「被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本一式」
「住民票の除票」「固定資産評価証明書」など。
加えて、相続人全員の戸籍や住民票も必要です。
遺産分割協議が必要な場合は、
協議書を作成し、相続人全員の署名・実印の押印と印鑑証明書を添付します。
そして、これらをもとに「相続関係説明図(家系図のようなもの)」を作成し、
法務局に申請書とともに提出します。
ただし、これらの書類はひとつでも記載ミスや不備があると受理されず、
再提出になることも。
必要書類の確認や記載方法は、
法務局の相談窓口やホームページでチェックできますが、
不安な方は専門家への相談がおすすめです。
専門家に頼む場合:司法書士・行政書士の選び方
相続登記を専門家に依頼する場合、
まず検討したいのが司法書士と行政書士の違いです。
司法書士は登記のプロフェッショナルで、
不動産の名義変更手続きをすべて代行できます。
複雑なケースや、期限内に確実に済ませたい方にとって心強い存在です。
一方、行政書士は登記そのものはできませんが、
戸籍の収集や遺産分割協議書の作成など、
事前準備のサポートを得意としています。
専門家を選ぶ際は、実績や口コミ、料金体系の明瞭さを確認しましょう。
「登記一式◯万円」などのパッケージ価格や、
初回無料相談を実施している事務所も多くあります。
不明点を丁寧に説明してくれるかどうかも大切な判断材料です。
家族に関わる大切な手続きだからこそ、
信頼できる専門家と一緒に進めることで、精神的な安心感も得られます。
費用の目安と助成金・控除制度の活用法
相続登記に必要な費用には、
大きく分けて登録免許税と専門家への報酬があります。
登録免許税は不動産の固定資産評価額の0.4%が基本で、
たとえば評価額が1,000万円の不動産なら4万円が税金としてかかります。
これに加えて、司法書士へ依頼する場合は3万~10万円前後の報酬が相場です。
依頼内容や地域によって変動があるため、事前の見積もり確認は必須です。
また、自治体によっては空き家対策や登記支援として補助金を用意しているところもあります。
さらに、不動産売却時には
「相続空き家の3,000万円特別控除」といった税制優遇も活用できる可能性があります。
こうした制度を知らずに損をすることがないよう、
登記だけでなく、税金や助成金についても司法書士や税理士に相談しておくと安心です。
「うちは複雑で…」という人こそ注意!よくある相続の悩み
相続は「財産を引き継ぐだけ」と思われがちですが、
実際には家庭ごとに異なる事情があり、
手続きがスムーズに進まないケースが多く存在します。
たとえば、兄弟同士が疎遠で話し合いができない、
過去にトラブルがあって連絡を取りたくない、
または遠方の土地で管理が難しいなど、
現実には“理屈通りにいかない”ことがたくさんあるのです。
特に、相続放棄をして「自分には関係ない」と思っていた人も、
実は手続き上は関わらなければならないケースもあります。
こうした誤解や放置が、後々大きな問題へと発展することも。
今すぐ解決できなくても、
「誰と、何について、どこが止まっているのか」
を把握するだけでも一歩前進です。
大切なのは、ひとりで抱え込まず、
専門家の力を借りながら“できることから”始めることです。
兄弟が疎遠/話し合いが進まない場合
相続人同士が連絡を取りづらい、話し合いがまとまらない。
そんな状況は決して珍しくありません。
特に、兄弟姉妹の関係がもともと薄かったり、
過去の確執がある場合、感情的な対立で協議が一向に進まないこともあります。
しかし相続登記には全員の同意や署名が必要になる場面も多く、
放置しておくと不動産の名義変更ができず、売却も管理もストップしてしまいます。そんなときこそ頼りになるのが、中立的な第三者である司法書士や行政書士の存在です。
彼らは感情的な対立から一歩距離を置き、必要な手続きを整理し、冷静に調整を進めてくれます。話がこじれる前に「間に入ってもらう」という選択は、後悔を防ぐ大切な判断です。
相続放棄したつもりでも登記は必要?
「相続は放棄したから、もう関係ない」
――そう思っていても、
正式な手続きが完了していなければ、
法的には相続人として扱われてしまう可能性があります。
相続放棄は、家庭裁判所に申し立てを行い、
正式に「受理」された時点で効力が発生します。
中には「口頭で兄弟に放棄すると伝えただけ」「書類は出したが控えがない」
といった曖昧なまま年月が過ぎてしまった例もあります。
さらに、放棄していたとしても、
登記手続きの補助(印鑑提供など)を求められることがあるため、
「もう完全に関係ない」とは言い切れないのです。
あいまいな認識は、将来的なトラブルの火種になりかねません。
まずは自分の相続放棄が正しく完了しているかを確認し、
必要があれば家庭裁判所や専門家に相談してみましょう。
土地が遠方にあり、管理できないケース
都市部に住む子ども世代が、実家や田舎の土地を相続した場合、
「場所も分からないし、現地に行くのも難しい」といった声が多く聞かれます。
そうして手がつけられないまま放置されると、
草木が生い茂ったり、不法投棄が発生したりして、
近隣から苦情が入ることも少なくありません。
さらに、管理できないままでも固定資産税は毎年発生し、
何もしなくてもお金と責任だけが積み重なっていきます。
こうした場合には、
地元の不動産会社や相続サポート業者に協力を仰ぐのが現実的な方法です。
現地調査や境界確認、売却の相談まで代行してもらえることもあります。
「遠いから何もできない」と諦める前に、
専門家の力を借りて“できること”から動き出してみましょう。
それが将来の自分や家族への思いやりにもつながります。
遺品整理士 倉島 新吾
東海3県~愛知県・岐阜県・三重県~ 九州エリア~鹿児島県・宮崎県・熊本県~
スケジュールに空きがあれば即日の対応も可能。お見積り無料です。
遺品整理、生前整理、空き家整理、ゴミ屋敷、汚部屋、特殊清掃(事故現場・孤独死現場)、
ウイルスの除菌消臭(新型コロナ対応)、ペット臭(猫屋敷など)、不用品買取値引き、解体前や退去前の残置整理 etc…
自転車・バイク・仏壇・神棚・マットレス・シンク・物干し台・物置の解体、撤去・エアコンの取外し・庭木の伐採・草刈りなどなんでもご相談ください!
TEL:0120-379-540 担当者直通:070-1327-8548
メール・LINEからは、24時間365日ご相談を受け付けしております。
Twitterも日々更新中♪
カメシタは公益社団法人被害者サポートセンターあいち(あいポート)に賛同しています。
新着記事
- [作業実績] [2026.01.28] 日進市:空家整理/戸建/2LDK
- [コラム] [2026.01.21] 「猫屋敷」の孤独に終止符を!プロの【まごころ特殊清掃】で愛猫と「普通の暮らし」を取り戻しませんか?【カメシタのハウスクリーニング】
- [作業実績] [2026.01.21] 東浦町:ゴミ屋敷清掃/賃貸
- [コラム] [2026.01.14] 名古屋市中村区:ゴミ屋敷整理/空家整理/戸建
- [コラム] [2026.01.14] 【多頭飼育ペットの遺品整理】母の愛は手放さない。途方に暮れるあなたへ、命と心を癒すプロの「まごころ」解決法